日本家屋のわずかな高低差が意味するもの
五十嵐太郎
-1024x768.jpg)
名古屋の本丸御殿
敷居とは、日本家屋、もしくは和室において、ふすまや障子など、スライドする建具のために床にとりつけられた溝やレールである。これと対になる枠の上部の方は、鴨居と呼ばれるが、足元の敷居の方が、しばしば慣用句として用いられる。例えば、「敷居をまたぐ」という場合は、物理的な行為そのものよりも、その家に入ることを意味する。したがって、「二度と敷居をまたがせない」というのは、出入り禁止だ。「敷居が高い」とは、高級すぎたり、不義理などをしてしまい、そこに行きにくい、入りにくいといったニュアンスをもつ。すなわち、ハードルが高い、ということだが、もちろん敷居という建築の部位は、数ミリ程度の高低差であり、シンボリックな表現と言えるだろう。また「敷居を踏む」は無作法という意味になる。そして「敷居越し」は、わずかな距離であることのたとえとしても使う。興味深いのは、「しきい」という音に対して、「敷居」だけでなく、「閾」という漢字もあてがわれ、同じ意味をもつ。ただし、後者の「閾」を「しきみ」と読む場合は、門の内外を区画するための門柱のあいだに敷く横木となり、「いき」として使うと、もっと一般的に内と外の境界をさす。
石や煉瓦を積んで建築をつくる西洋の感覚からすると、木と紙で構成された日本の伝統的な家屋はフラジャイルに見えるだろう。筆者の研究室では、窓学のリサーチ・プロジェクトを通じて、窓や開口部に関する建築家の言葉を収集した(『窓と建築の格言学』フィルムアート 社、2014年)。そこから日本家屋の特徴を巧みに表現した事例をいくつか紹介しよう。「壁はありませんから、特に窓というものはない。格子を適当にあけると窓になるわけです」(今和次郎)。「わが国の伝統的な木造建築は、いわゆる柱と梁の構成からなる軸組構造の建築であって、柱や梁でない部分はすべて開口部となりうるので、組積造のように穴をきりとるのではなくて、いかに穴をふさふのかということが、むしろ関心事となる」(芦原義信)。「西欧の扉は軋みながら重々しく開けられ、襖や障子は指先で音もなく滑るように開けられるのがいいとされる」(槇文彦)。「障子は光を透過する壁と考えることもできますが、それが動くことによって、開口部の形が様々に変わります」(香山壽夫)。

日本の文化財の用語に「柱間装置」という聞き慣れない言葉が存在する。これは柱と柱のあいだに取り付けられる建具の部位すべてをさす。つまり、雨戸、ふすま、障子などである。そして、これらをスライドさせたり、付けたり外すなど、重ね着したり、薄着をするように、気候によって風や光を調整するのだ。実際、すべてとり払うと、吹き放ちの開放的な空間になる。重い扉ではなく、敷居の上の軽やかな柱間装置は、決して内外を強力に隔てるものではない。だが、慣用句を確認したように、象徴的な意味を備えている。そもそも伝統的な日本建築は城や五重塔など、一部の例外をのぞくと、ほとんど平屋だった。藩主が暮らす本丸御殿にしても、西洋の宮殿のような圧倒的な空間の高さや壮麗な階段は存在しない。全体が平屋であるがゆえに、各部屋の床と天井の微妙な高さの違い、その仕上げ、装飾の差異によって、格式を細やかに演出している。また畳が普及する以前の平安時代は、百人一首の絵のように、板敷きの床であり、人が座る場所だけに畳を置き、畳の縁の色や文様が格式を示した。椅子も使わず、床のわずかな高低差が、決定的に重要だったのである。
窓学において古今東西の絵画を調べると、日本と西洋では空間の表現が大きく違う。西洋の肖像画では、人物の背景となる壁に窓があり、外の風景が見えたり、17世紀オランダの室内画では、フェルメールに代表されるように、自然光がさしこむ窓辺で作業する場面がよく描かれている。しかし、日本で同じような構図を探すと、意外なくらい見つからない。特殊な建築形式である茶室をのぞくと、壁に穴を開けた窓という概念が成立しにくいのも一因だろう。むしろ、吹抜屋台と呼ばれる、屋根や天井を省いて、斜め上から室内外を同時に俯瞰する描き方が、開口部付近のアクティビティを表現している。やはり、人工照明が十分ではない時代ゆえに、西洋と同じく、明るくなる柱間装置の近くに人々の活動がより多く認められた。すなわち、敷居とその外部に続く縁側や庭である。縁側は、家人が隣人や友人と交流する場所として使われた。例えば、昭和時代の国民的な漫画『サザエさん』の全45巻を調査したとき、磯野家の縁側を描いた183もの事例を確認したが、しばしば家族以外の人が訪れている。
現代の日本では、住宅のこうした縁側の使い方は減っているが、ヴェネツィアビエンナーレ国際建築展2016の日本館が「en[縁]:アート・オブ・ネクサス」をテーマとしたり、山﨑健太郎が設計した地域に開かれた福祉施設が「52間の縁側」と命名されているように、内外をつなぐポテンシャルをもつ場所だと認識されている。かつて磯崎新は、西洋の建築が頭上から光が降りそそぐのに対し、「光が日本では水平にバウンドしながらやってくる」と述べた。なるほど、近代以前の日本建築では、トップライトやハイサイドライトのような開口がない。その代わりに、深い庇で直射日光をカットしながら、庭の水面、あるいは縁側に反射しながら光が室内に入り込む。その内側の敷居は、日本建築ならではの心理的な障壁として存在する。だが、光や風にとっては無関係だ。逆に言えば、あえて敷居を踏むことができるのは、人間だけである。その小さな一歩は、大きく心を揺さぶるものになるに違いない。
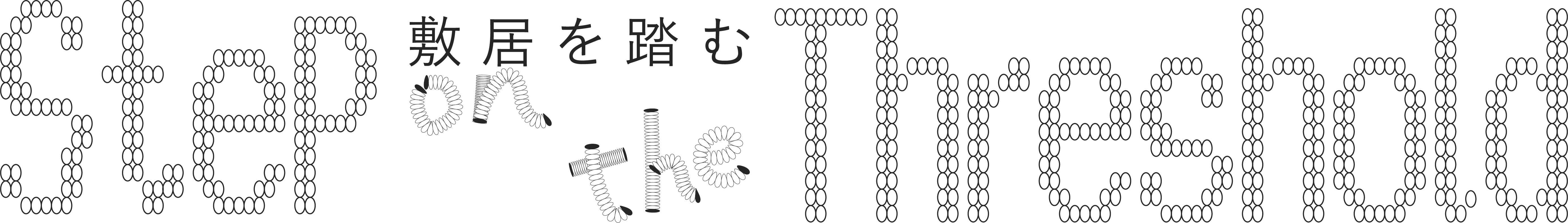
.jpg)