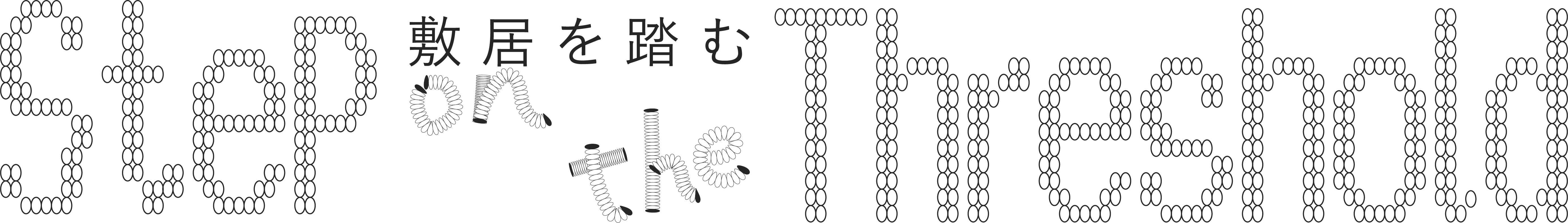上野公園をかきまぜる
近藤亮介

上野・公園・文化
上野公園を歩くのは難しい。上野公園には、藝術大学、博物館、動物園、奏楽堂、美術館といったさまざまな教育文化機関が集結し、毎日多くの人々で賑わっている。舗装は行き届いているし、噴水や不忍池の周辺は広々として見晴らしもよく、園内マップも標識も至る所にあるから迷いようがない。あらゆるものが秩序立てられた上野公園はたしかに便利だが、それ故に歩行のルートまで定式化されているように感じてしまう。実際、上野公園では何らかの建物を目指す人がほとんどで、屋外を一直線に横切っていく。
公園は本来、誰にでも開かれた雑多で散漫な場所である。近代の市民公園の先駆であるリヴァプールのバークンヘッドパークやニューヨークのセントラルパークは、労働者をはじめとする都市生活者のためにつくられた。それらは工業都市の生活環境を改善する手段として、自然を主体に設計された。同時に、公園は民主主義を醸成する場でもあった。社会階層の異なる人々が集い、相互理解を深める役割を担っていた。つまり公園では、普段は接しない自然や人と出会うことが期待されていた。
ところが、公衆衛生が改善すると、公園は平均的な市民の気晴らしに供するために文化的性格を強めていく。例えば、セントラルパークでは1920年代からスポーツ施設が整備され、50年代には野外音楽祭が開催されるようになった。同様に、上野公園でも1920年代から高度経済成長期にかけて多くの美術館や音楽ホールが建設された。ただし、明治期の日本にとっては公園そのものが西洋文明の象徴であり、しかも上野公園は近代化を推進する内国勧業博覧会場に選定されたため、最初から視覚・文化を強く意識した空間が構成されていた。このことは、現在の東京国立博物館・上野動物園・国立科学博物館が明治前期に創設された事実からも明らかである。
上野公園が日本初の公園のひとつに指定されたのは1873(明治6)年のことである。当初、公園を管轄したのは内務省で、1877(明治10)年8月の第1回内国勧業博覧会に向けて整備が進められた。博覧会場(現東京国立博物館の敷地)の構成は、全体として扇形で、表門を通り抜けると中央に噴水のある洋風庭園が広がり、庭園を取り囲むように陳列館が連なり、正面には美術館が建てられている(FIG. 1)。

会場の外では、表門前の敷地(現竹の台広場)に、馬車道と人道からなる通路が平行して3本敷かれた。南北の軸線を持つ幾何学式・対称型の空間構成は、上野に西洋近代の啓蒙的性格を注入した。
上野に投影された西洋近代的な公園像は、デザイン面のみならず、利用面からも窺い知ることができる。と言うのも、明治前期の上野公園ではたびたび明治天皇の儀礼が執り行われ、その結果として利用者の社会的属性を規定したからだ。1876(明治9)年5月9日には上野公園の開園を記念して明治天皇が行幸し、1年後の博覧会開場式では鹵簿を伴う盛大な式典が開催された。儀礼の際、公園は主に政治家や華族が集う場所となり、民衆は沿道に群がることしか許されなかった。つまり、上野公園は天皇を可視化し、国民国家を形成するための近代的装置として機能したのであり、卑近な都市生活者ではなく、標準化された国民へ向けられていた。この方針は、教育文化機関がひしめく今日の姿に通じている。
分かりやすい「文化」を求めてやって来る人々にとって、公園内の空地はただの通り道に過ぎないだろう。彼らは公園を気ままにぶらつくことはほとんどないし、公園ですれ違う人々や移ろう風景を観察することもない。他方、散歩などの日常的な機能を公園に求める住民は、人ごみを避けるために上野の山よりも不忍池を好むかもしれない。上野公園の過剰な文化志向が、来園者の平均化と棲み分けをもたらし、歩行の魅力を減じているように思われる。
しかし歴史を遡ると、上野はもともと遊覧的性格を備えていたのではないか。周知の通り、上野公園は東叡山寛永寺の境内地だった。寛永寺建立の目的は徳川幕府の守護にあったが、上野の山と不忍池を比叡山と琵琶湖に見立て、中之島や清水観音堂を築いたように、その境内地は寺院としてだけでなく、物見遊山や花見の場としても栄えていた(FIG. 2)。

また、台地の下には下谷広小路や山下と呼ばれる火除け地が設けられ、「盛り場」として賑わった。このように江戸時代の上野は、京都周辺の名所や見世物小屋、屋台が立ち並ぶ「テーマパーク」の様相を呈し、幅広い階層の人々が行き交っていた。彼らは、聖と俗が交差する上野で歩行を楽しんでいたはずだ。
ここで言う「歩行」とは、目的を持たない、あるいは歩く行為自体を目的とする「遊歩」のことである。庭園史家のジョン・ディクソン・ハントによれば、庭園ならびにデザインされた風景の中での動きは3つ――「行進・儀式(procession or ritual)」「回遊(stroll)」「遊歩(ramble)」――に分類される。行進または儀式は、宗教的ないし社会的な目的を達成するために、あらかじめ決められた道に沿って行われる。回遊は、特定の場所に目的が置かれ、動きを導くすべての事象のあいだに明確な経路が示される。遊歩は、個人の意思や好奇心に基づく歩行自体が目的となるため、決まった道や目的地は存在しない。さらに、これらの類型は風景の見方と密接に関わっている。例えば、回遊者は風景式庭園や大名庭園を象徴主義的に眺める一方、遊歩者は農村や郊外を自然主義的に観察する。
この分類に照らすなら、明治時代の行幸・鹵簿は「行進・儀式」に、江戸時代の参拝は「回遊」に、そして物見遊山は「遊歩」に当てはまる。だが、遊歩の様子はあまり詳しく記録されていない。それもそのはず、行進・儀式と回遊が特定のルートと複数の歩行者によって成立し、反復可能なのに対して、遊歩は不特定のルートと単独の歩行者を前提とし、一回性に依拠しているからだ。
遊歩・遭遇・感覚
遊歩者は、公園と同じく西洋近代の産物である。遊歩者として最も広く知られているのは、おそらく19世紀中葉のパリで生まれた「フラヌール(flâneur)」だろう。フラヌールは「のらくら者、ぶらつく人、怠惰な『町人』」を意味する(OED第二版)。この言葉を最初に用いたのは詩人のシャルル・ボードレールで、第2帝政期のパリをあてどなくさまよいながら、日々の出来事を観察する人物を指していた。しかし、フラヌールが想定するのは賃金労働とは無縁な有閑階級の男性であり、彼は都市をただ視覚的なスペクタクルとして眺めるだけで、土地や他者と直接関わろうとはしない。言わば「よそ者」である。
一方、イギリスには別の遊歩者、すなわち「ランブラー(rambler)」が存在した。ランブラーは、17世紀から「遊歩する人または動物」の総称として用いられ、現代では特に「娯楽として田舎を歩く人、しばしば仲間と一緒に決められたルートを歩く人」を意味する(OED第二版)。この定義は、18世紀に登場したピクチャレスク旅行者を想起させる。彼らはガイドブックを片手に「絵になる風景」を求めて旅する富裕者で、「よそ者」として対象から距離を取り、特権的なまなざしを向ける点では、むしろフラヌールに似ている。いや、そもそもピクチャレスク旅行者は風景観賞という明確な目的を持ち、長距離移動に馬車を利用したため、ランブラーとは呼べない。
今日ランブラーとして知られる人々が現れたのは、フラヌールと同じく19世紀中葉のことである。産業革命によって都市が飛躍的に発展した時代、労働者たちは公害や喧騒から逃れるために徒歩で田舎へ出かけるようになった。遊歩は当初、単なる気晴らしに過ぎなかったが、1930年代になるとランブラーは故意に富裕層の私有地へ不法侵入して「歩く権利」を主張し始めた。やがて遊歩は社会運動へと発展し、民有地か官有地かにかかわらず誰でも横断できる「公共歩道」を誕生させた。フラヌールとは対照的に、ランブラーは特権階級に抵抗する視点を持っている。
ただし、ランブラーが集団で歩く市民活動家となったのは近代のことであり、それ以前は単独で不特定のルートを歩く、言わば「はぐれ者」だった。事実、名詞「ランブラー」に先行する動詞「ランブル(ramble)」は、まず「精神的な探求や研究に関して、非体系的な方法で、しばしば明確な目的なしに、熟考すること」を表し、のちに「身体的な探求に関して、明確な目的や方向を持たずに、自由奔放にさまようこと、または旅行すること」という意味も持つようになった(OED第二版)。要するに遊歩という行為は、決まったルートや手順にとらわれることなく、むしろ非体系的で自由奔放、ときに支離滅裂な思考・記述・歩行を導く。
この原義を最もよく表しているのは、セントラルパーク中心部につくられた森林「ランブル(The Ramble)」だろう。その森林は、劣悪な都市環境から抜け出す余裕を持たない労働者の保養地として、ニューヨーク州北東部のアディロンダック山地をモデルに設計された。セントラルパークのデザインは、イギリス由来の風景式庭園を基調とするが、わけても「ランブル」は園路が細く曲がりくねり、生い茂る植物も相まって、錯綜した風景を生み出している。
アーティストのロバート・スミッソンは、1973年に「ランブル」を歩いたときの所感を次のように記している。「彼〔セントラルパーク共同設計者のフレデリック・ロー・オルムステッド〕がこの場所全体に縒り合わせた小道のネットワークは、迷宮を超えた迷宮だ。ランブルとは、当てもなく無為に歩くための場所のことでなくて何だろうか――それはあらゆる方向に広がる迷路なのだ」。実際、そこに足を踏み入れた途端、人は情報過多な都市から遮断され、方向感覚を失い、さまようことになる。そうして歩くうちに、遊歩者は足から伝わる地面の凹凸、鳥の鳴き声、植物の匂いといった目に見えないものへと意識を傾けるようになる。また、予想しない人物に出会うこともあり得る。スミッソンは続ける――「今やランブルは都会のジャングルに成長し、その茂みには『ちんぴら、浮浪者、売春者、同性愛者』など、街の疎まれた奴らが潜んでいる」。このように多様な人間を受け入れ、断想や遭遇を生じさせる「ランブル」は、遊歩ひいては公園の本質を体現した空間と言える。
とは言え、現在の整然とした上野公園には「ランブル」のような入り組んだ場所はない。道は均され、案内板があちこちに設置されている。皇族が教育文化機関を行幸啓する際に実施される特別清掃「山狩り」の厳格化によって、ホームレスさえ居場所を失いつつある。それでもランブルを実践することはできる。ここで参照したいのは、小説『JR上野駅公園口』における主人公の歩行と語りである。福島出身の出稼ぎ労働者だった主人公は、67歳で家を捨てて上野公園で暮らすホームレスとなった。日々、彼は公園周辺をぶらつきながら観察と回想を繰り返す。
男の語りを特徴づけるのは、歩く道すがら偶然見かける出来事や人が、記憶や感情を呼び起こす引き金となっていることである。動物園の前では幼い子どもたちと遊んだ記憶をたどり、身綺麗なホームレスを見たときには知人のホームレスとの交流を懐かしみ、雨が降るたび息子や妻を亡くした日に思いを巡らす。社会の中ではぐれた男にとって、歩行と思考は不可分であり、かつ歩行は思考に先行する。しかも、歩行の経験を豊かにしているのは、時間をかけて聞く態度である。「話すことは、躓き、迷い、回り道や行き止まりばかりだけれど、聞くことは真っ直ぐ――、いつでも耳だけになれる」と言うように、男は通行人の会話、ラジオのニュース、木々のざわめきといった身の回りの音にしばしば耳を澄ます。視覚よりも身体へ直接働きかける聴覚を通じて、現在と過去の時間はないまぜになる。そのとき彼は、たしかに身体と精神の両面において「ランブル=遊歩」している。
上野公園を遊歩することは、明治政府が統制しようとした「国民」ではなく、大衆から距離を取る特権的な「よそ者」でもなく、出来事と不意に出会う「はぐれ者」になるということである。はぐれ者は、ホームレスとは限らない。普段は文化を求めて一直線に歩いている人でも、目的なしに歩き回り、視覚に頼らず土地や他者を感覚すれば、一時的にせよはぐれ者になることができる。ひとりひとりの遊歩が、上野公園をかきまわし、上野および公園が本来備えている多様性・錯綜性を浮かび上がらせる。
[図版キャプション]
FIG. 1:博覧会場諸建築並売店図(1877年)
出典:国立公文書館
FIG. 2:東都名所 東都八勝 上野晩鐘(江戸時代後期)
出典:国立国会図書館
[参考文献]
Hunt, John Dixon, ‘“Lordship of the Feet”: Toward a Poetics of Movement in the Garden,’ in Landscape Design and the Experience of Motion, edited by Michel Conan (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2003), pp. 187-213.
———, “Time of walking,” Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 36.4 (2016): 297-304.
Jackson, John Brinckerhoff, Landscape in Sight: Looking at America, edited by Helen Lefkowitz Horowitz (New Haven and London: Yale University Press, 1997).
Smithson, Robert, “Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape,” Artforum (February, 1973): 62-68.[ロバート・スミッソン「フレデリック・ロー・オルムステッドと弁証法的風景」平倉圭、近藤亮介訳、『美術手帖』vol. 74 No. 1094(美術出版社、2022年6月)、113-36頁]
Solnit, Rebecca, Wanderlust: A History of Walking (London and New York: Verso, 2001).[レベッカ・ソルニット『ウォークス――歩くことの精神史』東辻賢治郎訳(左右社、2017年)]
小野良平『公園の誕生』(吉川弘文館、2003年)。
木下直之『戦争という見世物――日清戦争祝捷大会潜入記』(ミネルヴァ書房、2013年)。
桑田光平「歩くこと――「人間の尺度」の回復」、桑田光平、田口仁、吉野良祐編『東京時影1964/202X』(羽鳥書店、2023年)、24-48頁。
近藤亮介編『セントラルパークから東京の公園を見てみよう』(公益財団法人東京都公園協会、2023年)。
白幡洋三郎『花見と桜――〈日本的なるもの〉再考』(八坂書房、2015年)。
鈴木博之『東京の地霊』(筑摩書房、2009年)。
ベンヤミン、ヴァルター『パサージュ論(三)』今村仁司、三島憲一ほか訳(岩波書店、2021年)。
—————『ベンヤミン・コレクション1――近代の意味』浅井健二郎編訳、久保哲司訳(筑摩書房、1995年)。
柳美里『JR上野駅公園口』(河出書房新社、2014年)。
吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー――東京・盛り場の社会史』(河出書房新社、2008年)。