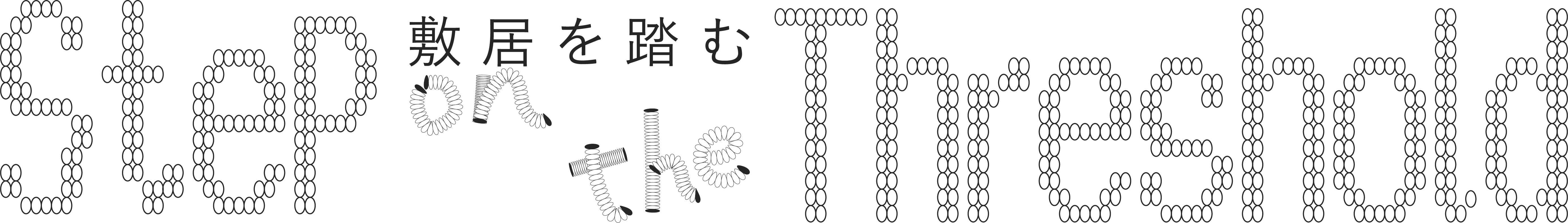外に出て歩くということ
長島確

「敷居を踏む」と題する本展覧会のキュレーターとアーティストたちがウォーキングツアーを企画している。これを書いている現時点でまだ全貌はわからないけれど、とても楽しみな試みなので、わたしの専門領域のパフォーミングアーツの側から、いくつか関連するかもしれない経験を書いてみたい。
近年の日本のパフォーミングアーツ(とくに演劇)の文脈では、2000年代前半から、観客が歩行しながら体験する作品が散発的に現れている。岸井大輔による「ポタライブ」が早い例で、その後Port Bによるツアーパフォーマンスがあり、わたし自身も三宅島でおこなった「アトレウス家」のプロジェクトや、中野成樹(+フランケンズ)による四谷や松戸での上演に関わっている。スタッフまたはパフォーマーが引率する場合もあれば、観客が地図や音声ガイドを頼りに自力で巡る場合もある。散歩型または移動型に限定しなければ、野外劇の伝統は古くからあるし、近い文脈では「書を捨てよ町へ出よう」と言った寺山修司による市街劇が1970年代にあり、美術ではさらにひとまわり昔のハイレッド・センターなどに遡ることができる。
通常、劇場からパフォーマンス(演劇でもダンスでも何でもよい)を外に持ち出すと、まず何が起こるかというと、膨大な夾雑物が出現する。「作品」もしくは「上演」の中に、「作品ではないもの」「上演ではないもの」が大量に混ざり込んでくる。パフォーマーの後ろを自転車が通ったり、近くの工事現場の音が聞こえてきたり、雨が降ってきたりする。観客も、それらをまさか仕込みとは思わないだろう。実際仕込みではない場合がほとんどだが、作り手も観客も、そういう偶発的な混入物を歓迎するか、拒否するか、態度が問われる。
例えば、周囲の音がうるさくてせりふがよく聞こえない。演技・演奏に集中できない。遠くて、または何かの陰になってよく見えない。寒い。車が通って気が散る、等々。マイクやスピーカーを用いず機械的な増幅によらない繊細な表現(とくに演劇のせりふやある種の音楽)は、劇場の外へ持ち出すと驚くほど脆弱である。言いかえると、「表現」に勝る圧倒的なノイズ(音に限らない夾雑物)に世界は満ちている。
「作品」への集中を妨げるさまざまなノイズを邪魔だと思うなら、当然それらを排除する必要がある。劇場などの「専用施設」が便利なのはここだ。見せたいもの、聴かせたいもの以外のすべてを排除することができる。パフォーミングアーツの業界で「ブラックボックス」と呼ばれる、壁面も床も天井も真っ黒な箱型の上演空間は、その極端なひとつの達成だろう。美術のホワイトキューブも同じ思想だ。専用施設は外界のノイズを遮断し排除する、フィルタリング装置のようなものである。そこで何が排除されているかは考えてみる価値がある。観客も不動と静寂を求められる場合がある。
逆に、外のノイズを歓迎してみよう。上演中、たまたま吹いた風、たまたま上空を横切った飛行機が、やたらと劇的に見えることがある。偶発事がもつこうした効果は非常に魅力的であり、作り手もある程度それを当てにして作ることもある。偶発事の混入する余地、余白を残して作るのである(画面の一部を塗り残しておくようなものだ)。
もちろん劇的な偶発事は、そんなに都合よく起こるとは限らない。けれども、施設内とちがって、外に出た観客は、仕込みではない膨大な情報にいやでも曝されることになる。ふだんの生活では無視している膨大な事物のディテールが、いちいち何か意味をもって現れてくる。だから、必ずしも「劇的な偶発事」が起こらなくとも、鑑賞すべきものはいくらでもあるとも言える。そんなふうに知覚のスイッチが入ってしまうと、在るもの、起こること、すべてが作品に見えてくる。世界がキラキラ、ふわふわしてくる。
この多幸感と開放感はすばらしいものだけれど、同時に危険も潜んでいる。スイッチの入ってしまった観客は、すべてを鑑賞対象と思い込み、通行人をじろじろ見、地元住人の家をのぞき込み、写真を撮り、他人の生活空間で、まるで自分は透明人間になったかのように振る舞い始める。作り手も、そこにあるすべてを自分の作品の素材のように思い込む。ともに収集者、簒奪者となって、大航海時代の負の側面をくり返しかねない。生活空間はアーティストや観客の遊び場ではないのだから、専用施設の中だけでやっていろ、という話になる。
しかし臆病になりすぎることはない。まちのなかにもさまざまな「表現」があり、アクションの痕跡がある。住人によるものもあれば、よそからやってきた誰かによるものもある。人間ではないものによる場合もある。それらに何を見て取るのか、何を付け加えるのか。それは外に出たアーティストやキュレーターの仕事でもあり、同時に鑑賞者自身の積極的な行為でもある。
劇場や美術館の内と外の境界線はわかりやすいけれど、その外のあちこちに「一線」があるのだ。超えてみるべき一線と、超えるべきではない一線がある。その理由も、法律的だったり、倫理的だったり、純粋に美学的だったりする。これらの線は、必ずしも明確に、こちら側と向こう側を分け隔てているわけではない。線自体に太さや滲みがあって、その幅のなかに身を置くことができるかもしれない。切れ目もあるのかもしれない。
専用施設から出て外を歩くとは、透明人間にならずに(自分も社会の一部であることを忘れずに)、しかし生活者とは別の目をもって、この曖昧なゾーンに踏み入ることである。今回のウォーキングツアーが、ノイズから守られた館内の展示と相まって、刺激的な体験になることを楽しみにしている。
長島確
ドラマトゥルク
東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科准教授