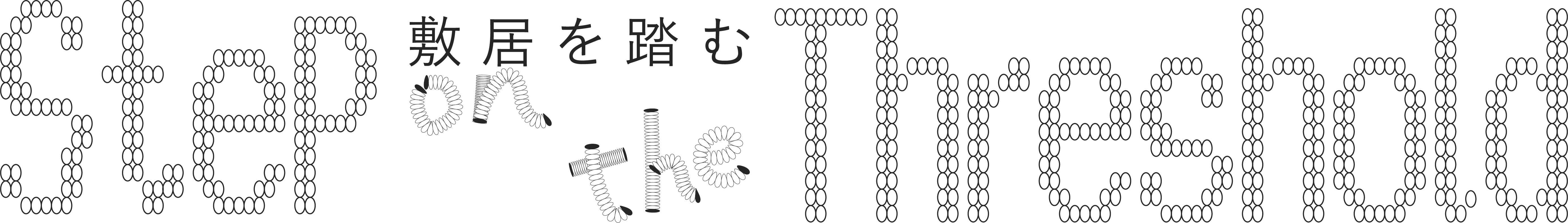敷居=境界に立って
渡部 葉子

Sculpture Garden at Kroller-Muller Museum
「敷居を踏む」というのは聞き慣れぬ物言いである。高かったり、低かったりする敷居は、跨ぐもので、踏んではいけないと言われて来た。敷居を踏むことは作法に反する行いである。そこを敢えて「踏む」という訳である。辞書(『大辞林』第四版)によれば、敷居は「 門の内外を区切り、また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖などを受ける」と説明されている。領域を分ける境界が敷居であり、それを踏むことは、領域区分をないがしろにする行為として忌避されるということだろう。それは必然的に敷居=境界そのものをある意味で神聖視し、触れ難いものにした。内/外というとき、基本的には内が自分のテリトリー=帰属領域であり、外はその外周、外側である。ウチ=家(ホーム)とその外側(=外界、世間)と考えれば分かりやすい。敷居の言葉が家制度と関連して使われていることも典型的である、「敷居をまたがせない」と言われれば勘当である。ウチ(内=家)に立ち入らせない、関わりを持たせないことを示している。では、作法を破って敷居を踏んで、境界に立ってみようではないか。敷居を踏む=境界に立つということは、区分された領域のどちらにも属さないところに居ることを意味している。内を見ることも、外を見ることもできる、ある意味でニュートラルで見晴らしの良い場にいる(=両領域のルールから自由である)ことになる。塀という区切り=境界に上ればそれは更にハッキリする。高い位置にいるから見晴らしが良いのは当然だが、それは木に登った時の見晴らしとは違う、内側でも外側でもない場所にいる不思議な浮遊感を伴った見晴らしの良さである。
境界に在る浮遊感——既存のルールから自由なのは、しがらみがないが、心許ないことでもある。「敷居を踏む」というモチベーションは、境界がその効力を失ったから現れたのではないか。つまり、領域区分が明確でなくなったから、その区切りである境界=敷居そのものが問われることになったのではないか。そして、今やそもそも敷居で区切られていることが共有されているかどうかさえ、怪しいのではないか。あるいは、敢えてその敷居をずらしたり、見えなくしたり、見ないようにしたりして、アートの領域が複雑に拡大しているのではないだろうか——多様化といい、多元化といい、多視点的と形容したりする。
唐突だが、聖書の有名な言葉に「汝の隣人を愛せよ」(マタイ福音書22章38節)という一節がある。この一節について、何十年も前に教会である神父が語った説話が印象深く心に残っている。一体「隣人」とは誰なのか、と言うのである。コンパスで円を描くとして、私たちは自分を中心として円を描いて隣人の範囲を想定する。しかし、隣人とは相手が引いたコンパスの円の中に自分が取り込まれるかどうかで決まる、と言うのである。自分が想定しない人が描いた円に含まれたら、そこで「隣人」認定されると言うことになる。領域ということを考えていて、急にこの話を思い出した。自分が意識的にその領域に境界を跨いで入らなくても、境界線のほうからやってきて、気がついたらその領域に取り込まれていると言う訳である。いま、様々な領域の境界はそのような状況を迎えているのではないか。アートという領域をどう見定めたら良いのだろうか、それは複雑に重層的に領域をずらし、ずれ重なっているのではないか。自分が捉えている領域は著しく個人化して、人との共有がおぼつかない様にも見える。個別化された領域の集積の中に居る。分類が行われ領域が明確に示され、記述された時代が去り、デジタル環境の中で、体系的分類を踏まえない取り出しが行われる時代に居るのである。そこで暫定的領域=グルーピングを形成するのは取り出しに対応する、様々に付与されたタグである。つまり、敷居の有りよう自体が変わってしまったのである。このような観点に立てば、今回の展覧会の特徴であるフットノートはタグ的役割を果たしつつ、それが何に付与されているか明示されないことによって、更なる境界の曖昧化の作用を及ぼす。そして、それはモノに対する認識の再構築を求めることになるといえよう。
元来、美術館内営為であった展覧会は今や、美術館を含む活動となっている。展覧会と美術館の関係は逆転し、展覧会は外へ外へ、作品鑑賞という典型的美術館的行為を大きく超え出て久しい。一体何が展覧会の提示物=exhibisなのか、今回の展示でも、そこに自覚的に出入りを仕掛けて曖昧さを助長しながら観客/参加者に参画的思考を促そうとしている。もはや見出すことが時に困難な敷居を敢えてその曖昧さのなかで見出して踏み、そこに立って見渡す一歩こそ、現状での創造的な応答のために求められることなのだろう。